闘う経済アナリストがわかりやすく解説
老後資金不安を解消するには まず具体的な数字を把握する
文 = 森永康平(マネネ CEO)/ text by Morinaga Kohei
2022年4月から高校でも金融教育が始まった。最近では昨年から始まった新NISAを契機に、20代でも既に投資をして将来のための資産形成をしている人をよく見かける。一方で、30代~40代の方から私のもとに寄せられる質問の多くは、「老後資金をどのように準備すればよいか」というものだ。日本では金融リテラシーの格差が年代によって開いている可能性がある。
私のもとに老後不安の相談する方に何が不安なのかを聞くと、特に具体的な話は出てこず、なんとなくぼんやりとした不安を抱えているとの回答が多い。そこで、毎月の手取りの収入や固定費、変動費をひとつずつヒアリングしながら、将来設計のプランニングをしようとすると、驚くことに自分の毎月の収支をしっかりと把握している人があまりいないのだ。それでは相談に乗りようがないので、次回の相談までに全てのデータを持ってきてもらい改めて将来設計のプランニングをすると、人によっては想像していたよりも悪い結果(すなわちお金の不足が明らかになる)が出てしまうこともある。
>>記事全文は『Amusement Business Answers』(2025 SUMMER Vo.1 No.3)でお読みいただけます。

■ 森永康平
経済アナリスト、株式会社マネネCEO。証券会社、運用会社にてアナリストとして株式市場や経済のリサーチ業務に従事。2018年6月、金融教育ベンチャーのマネネを創業。『スタグフレーションの時代』(宝島社新書)、父・森永卓郎との共著『親子ゼニ問答』(角川新書)など著書多数。














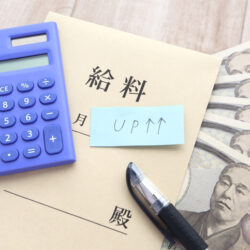
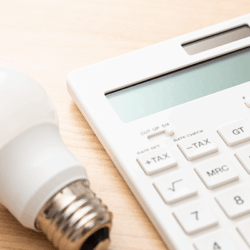

コメント